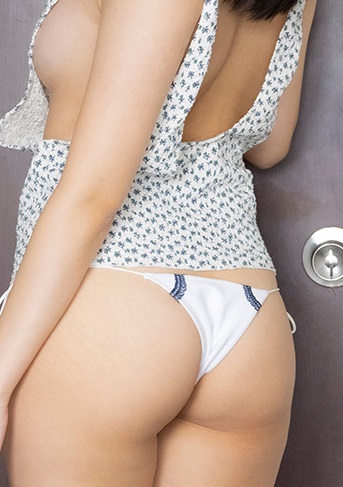まるで夢遊病者のようにフラフラと、隆志は正門に向かって歩いて行った。すれ違う学生たちには目もくれずに、隆志は今しがた起きた出来事、美和子のことを悔やんでいた。
(オレが早とちりしていらないことをしたばっかりに、決定的に嫌われちゃった。もう取り返しがつかないよ)
悔やんでも悔やみきれない後悔の念で、隆志は半分泣きそうになった。
(冷静に考えてみれば、あの美和子が黒い噂の山下と付き合うわけないじゃないか。最初からそういう前提で話をすれば、これがきっかけになって、美和子ともっと仲良くなれたかもしれないのに…。オレは本当にバカだ)
隆志は自分の愚かさに、大声で叫びだしたい気持ちになった。
その時、いきなり後ろから肩をトントンと叩かれた。驚いて振り返るとそこに美和子が立っていた。
「あのさ、新谷君はまだ話したいことがあるんじゃない?」
「…」
「ちょっとついてきてよ」
突然のことでぽかんとする隆志を尻目に、美和子は隆志を先導するように速足で歩きだした。隆志は慌ててついていった。
美和子は大学の正門をくぐらずに、そこから左側へ回り込んでいる小道を歩いていった。少し離れて、隆志はその後姿を追いかけた。サンドベージュのブルゾンの下には、下半身にぴったりと張り付くスリム・ジーンズに包まれた長い脚がある。適度にムチっとしている太腿の上には、お尻がまるまると張り出していて、すれ違う人が振り返って見たくなるような、美和子はまさに「映える」後姿の女子大生だった。悪夢で見た渋谷の道玄坂を山下と歩いていた美和子とは違い、実際の美和子は男に媚びを売るようにお尻をフリフリして歩くのではなく、まるでアスリートのような鮮やかな足さばきでスタスタと歩いていく。それは思わず見とれてしまう美しい足さばきだった。
大学の外周に沿って校舎を回り込む小道の先に、大きな木製のアーチが見えてきた。そこは美和子の大学が隣接する運動公園の入口だった。美和子はスタスタとその公園の中に入っていった。
400メートルの陸上トラックを見渡す場所に大きなポプラの木があり、その根本にベンチが置いてある。美和子は当たり前のように、そのベンチに腰を下ろした。遅れて来た隆志も、遠慮がちに隣に座った。
「ここは穴場なんだ。人があんまり来ないし、お弁当を食べるのに最適な場所」
美和子が明るい口調で説明した。その様子に、隆志はひょっとしたら決定的に嫌われてないのでは…、という淡い期待を持った。
「広くて、気持ちがいいね」
隆志は腫れ物に触るように、さしさわりなく話し始めた。
「そうでしょ。トラックはうちの大学の体育会や同好会の人たち以外にも、社会人や中高生も使っていて、練習を眺めていると結構面白いんだ」
「山本は陸上やったっけ?」
「私は走るのダメ。でも泳ぐのもたいしたことないから、運動が全部ダメってことだね」
そう言って美和子が笑った。つられて隆志も遠慮がちに笑った。
「新谷君、さっきは一方的に怒鳴っちゃって、ごめんね」
「気にしないで。山本が怒るのは当然だよ」
美和子が冷静に戻った様子なので、隆志はまずはほっとした。
「ちょっと考えたら新谷君が、私が山下と付き合っているというデマを流したわけでもないし、怒ってごめん。それで、それとは別に新谷君が今日ここに来てくれた理由があるんじゃないかと思って…。その肝心な話を、私は全然聞いてないよね。だからそれを聞きたくて…」
そう言われて、隆志はすぐに返事が出来なかった。
(何から何を話せばいいんだろう。でもグズグズしていたら、折角、美和子がくれた時間をまた台無しにしてしまう)
隆志は覚悟を決めることにした。洗いざらい美和子に話して、自分の中で抱えていた気持ちをぶつけようと決心したのだ。
「今日、ここに来たのは二つ理由がある。まず、黒い噂がある山下とつきあっていると誤解して、それを阻止しようと思ったこと。余計なお世話だけど、山本が山下なんかとかかわるのは絶対にダメだと思ったんだ。でも、なんでそんなことオレが勝手に思うのか…そこが不思議だよね」
美和子は答えずに、優しい目をして隆志を見つめた。
「それが二つ目の理由で、なぜかと言えば、オレが山本のことを好きだから。実は高校一年の時に初めて山本と会った瞬間から、オレは山本のことが大好きだった」
「…ほんとに?」
ちょっと緊張して聞き返してくる美和子は、息をのむほど美しかった。
「本当だよ。嘘はつかないよ」
隆志の中で大きな力が働いて、普段は恥ずかしくて言えないようなことも、不思議と自然に口をついて出てきた。
「同じクラスになったことはないけど、ずっと好きだった。それで卒業してからも、大学に入ってからも、ずっとずっと、山本のことだけが好きで、どっかでまた山本と会える気がしていたんだ。勝手な妄想だけど…。それで今でも大好きだから、今日は、これからも会ってくださいって頼みにきたんだ。そのために連絡先教えて下さいって…つまり、そういうこと」
美和子が好きって何回言っても、隆志は言い足りない気分だった。
「ありがとう。…うれしいよ」
「ええっ、ホントに?」
「本当だよ。実は私も高校の時から、ひょっとしたら新谷君は私のことが好きなんじゃないかと思ってた」
「オレが、同じクラスでもないし、ろくに喋ったこともないのにジロジロ見てたから、気味が悪かったよね」
「見られていたのは知ってたけど、それは全然いやじゃなかったよ。それより新谷君の声とか喋り方とか時々耳にしてて、すごく優しい感じで、聞いてて気持ちがよかった。だから…私もろくに喋ったことないのに、高校の時から勝手に新谷君が好きだった。これが真実」
「ええっ。そんなことってあるかよ」
「驚くよね。これ人に喋ったの初めて。でもカツ子から、ずっと新谷君の噂は聞いていたんだ」
「そうなの」
「うん、カツ子とは1、2年と同じクラスで、そこからずっと友達。新吉君との結婚式は家族旅行があったので出席できなかったけどね。幸せになれて良かったよ。カツ子は入学以来、新吉君一筋だったから。それでいつも新吉君のそのそばにいた新谷君の噂を聞いていた、というかカツ子を誘導して聞き出していた。ふふふ、驚いた?」
「驚いたよ」
「カツ子から、美和子も彼氏作るなら隆志がお勧めだよって、よく言われたの。私たちの間では新吉と隆志って、セットで呼び捨てにしてる。ごめんね」
「いいよ。うれしいよ」
「しかもまだ私の話は続くの」
そう言って、美和子は楽し気に話を続けていった。
「隆志君が頑張って難関の大学に受かって、背も高くなって。同窓の女子のなかで、ちょっとした噂になってたの知ってた?」
「いや、全然知らなかった」
「それで私もどんどん気になっていったんだけど、隆志君と会う機会はないし、今みたいに二人で話ができる日が来るなんて思ってもみなかった。ところがカツ子が、夏休みになると隆志君がよく図書館に籠っているって教えてくれたの。それで勇気を出して、あの日初めて私も図館館に出かけてみたら、本当に隆志君が来て隣に座ったからびっくりした」
「ええ、そうだったの」
美和子が隆志に会いに図書館に来たという告白に、隆志は驚いた。そしていつの間にか美和子が隆志君と呼びだしたことが嬉しかった。
「そう、実はあの日、私は隆志君に会いに図書館に行ったんだ。運よく会えて、話すことが出来て、しかも映画にも誘ってもらった。その映画館で、ああこの人、私のこと好きだなって確信したの。どうしてだか分かる?」
「ええ、どうしてだろう。オレ、変なこと言った?」
「そうじゃなくて、隆志君、映画館で私の腕に触ったでしょ」
突然、言われて隆志はとまどった。自分の下心を見透かされたようで、恥ずかしかった。
「最初は隆志君の肩と私の腕が偶然当たっただけだと思ってたら、それから隆志君の肩が離れなかったよね。私が押しても引いても隆志君の肩がくっついてきて、それが可笑しくて。あの映画面白かったけど、隆志君がずっとくっつくのが可笑しくて、半分それで笑ってた」
思い出したように笑いながらそう言う美和子が、隆志は嬉しかった。
「あと花火に誘ってくれた時も…」
「手がくっついたよね」
今度は隆志がすかさず言った。
「そう、それも映画館と同じでずっとくっついていたけど、花火の時は、最初は私がわざとくっつけたの。あの時、私が何考えてたか分かる?」
「うーん、分からない。またオレの様子が滑稽で、おかしかったとか」
「違うよ。手を握ってくれればいいのにって思ってた」
「えええっ」
美和子の意外な告白に、隆志は仰天した。
「あのね、よく考えて。女の子が何でもない人と、二人っきりで映画に行ったり、花火に行ったりすると思う?しかも花火には、私、浴衣着て行ったんだよ」
(言われてみれば、その通りだ)
隆志は、自分の自信のなさ、気の利かなさが情けなくなった。
「でも花火の後、隆志君は次の約束をしてくれないし…」
「それはごめん。山本と花火を一緒に見れたことがあまりにも楽しくて、もう夢の中だったから」
隆志は慌てて謝った。
「本当にうっかり次の約束をするの忘れて。でも山本の連絡先も知らなかったから、家中探したけど、高校時代の名簿なんてそもそもなかったし。それで新吉とカツ子のことを思いついて、本当はカツ子に山本の連絡先を聞こうと思って、新吉を誘ったんだ。そしたらカトーがデマを飛ばしてきて…」
「そうだったんだ。隆志君も私のことを好きになってくれていてよかった。ありがとう」
「いや、お礼をいうのはオレの方だよ。ありがとうね」
「あのね。隆志君は女の子と手をつないだことある?」
いきなり核心をつく唐突な質問に、隆志はドキリとした。
「ないよ」
「じゃあ、キスしたことは?」
「そんなの、あるわけないでしょ」
(妄想の中では、山本と何回もキスしてる)
隆志は顔を赤らめた。
「そうだよね。私もないの。生れてから一度も、誰とも付き合ったこともない」
「オレもだよ。女の子と付き合ったことないよ」
真っ赤になって答える隆志に、美和子は安心した口調で続けた。
「うちの両親は小学校の同級生同士なんだ。小学校5年の時に付き合い始めて結婚した」
「へぇー凄いね」
「それで今でも私や妹が呆れるくらい仲が良くて、それがいいなぁと思ってる。私もそういうのがいいなぁと思ってるの」
「そうだね。理想的だよね」
「そうでしょ。だから隆志君と私も誰とも付き合ったことなくて、このまま一緒に生きていけたらいいなぁって、勝手に空想してた」
「それ空想じゃないよ。まさしく、おれの願望だよ」
隆志ははっきりと本心を口にした。
「だったらこれからは、私のことだけを見てくれる」
「もちろんだよ。今までだってそうだし、夢にだって山本以外が出てきたことないよ」
「ははは、夢はいいけど、現実では絶対に私だけを見つめて欲しいの。それを態度で示してくれたら、私は一生、隆志君と生きていきたい」
「ああ、わ、わかったよ。絶対によそ見しないから、よろしくお願いします。ずっと隣にいてください」
「よし」
美和子が立ち上がった。
「ねぇ、コーヒーでも飲みに行かない?」
「いいけど、授業はいいの」
「今日は、授業はない」
「ええっ」
「実はカツ子が教えてくれたの。隆志君が大学で私を待ってるはずだって。何の用事かは教えてくれないからカツ子の嘘かと思ったけど、ワクワクして来てみたら本当にいたから驚いて…、嬉しかった」
(そういうことだったのか)
まんまと新吉とカツ子にはめられた感じの、自分が嬉しかった。そして隆志も立ち上がり、二人で爽やかな秋の日差しの中を歩き出した。
「ねぇ、手を繋ごうよ」
美和子が突然そう言うと、右手を下からすくうようにして、隆志の左手を握ってきた。
(うわぉ、美和子の手だ。手をつないでる。柔らかくて優しい手だ)
隆志は興奮した。
「始めに言っとくけど、知ってると思うけど、私大きいから時々腕に当たるけど、気にしないでね」
(ええ、大きいって、それってオッパイのことですか?美和子からそんなこと言うなんて素敵すぎます…)
隆志はドギマギした。
「こんな風になっても、それは私の気持ちだって思ってくれていいよ。ふふふ」
美和子が繋いでいる腕を内側にひねった。隆志の腕が巻き取られて、美和子の胸の膨らみに密着した。
(うわわわわわ、これはくっつくなんてもんじゃない。腕がオッパイに食い込んでるよ)
腕の下にはっきりと感じる美和子のオッパイの肉感に、隆志は大興奮した。その感触を逃すまいと姿勢を固くして、隆志は美和子に寄りそうように歩いた。幸せ過ぎて、気持ちよすぎて、このままどこまでも、永遠に歩いていきたい気分だった。
「よかったら私のこと、美和子って呼び捨てにして。私も隆志って呼びたいから」
「いいよ。いきなりは恥ずかしいから、最初は美和ちゃんでいくよ」
その正直な答えに美和子が笑った。
(こんな日が来るなんて、人生は何が起きるかわからない。だから生きてるって素敵なんだ)
この日、隆志がこれまで生きてきて一番幸せな瞬間、一生忘れられない秋が訪れた。 (終)